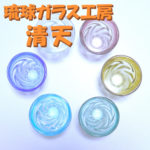泡盛の貯蔵方法について

甕・樽・タンク
それぞれが異なる風味に育ちます。
今回は製造された後の泡盛についてのお話です。
酒造所で作られた泡盛は、味を調えるために一度涼しい場所で寝かせます。というのも、出来立ての泡盛は非常に刺激が強く、ちょっと飲みづらい。。。
古酒でなくとも通常は数か月から1年程度は寝かせてから販売されるのが通常です。
泡盛は寝かせた年数によって古酒と呼ばれるものとそうでないものがあります。3年以上寝かせた泡盛を古酒、3年未満のモノを一般酒(新酒とも呼ばれていました)と呼び区別しています。
また、3年以上寝かせた泡盛を使用していても、一般酒がわずかでも配合されていれば古酒と呼ぶことは出来ず、混合酒(ブレンド酒)と表現されたりします。つまり、3年以上寝かせた泡盛が100%入って古酒と呼ばれると言う訳。
ブレンド酒の中でも一般酒と古酒のブレンドもあれば、古酒どうしのブレンドもあり、ラベルにその割合が記載されていることもあります。
そして、寝かせる環境や方法によって風味が大きく変わっていきます。今回はその貯蔵方法について見ていきましょう。
樽貯蔵

まずご紹介するのが樽を使った貯蔵方法。
泡盛に樽の香りがうつり洋酒のような風味に育ち、琥珀色の奇麗な色合いに染まっていきます。
樽を使った貯蔵は古くから行われていましたが、近年はそのバリエーションも豊富になり、単に寝かせるだけではなく熟成させたアルコールを原酒としてリキュールを造る酒造所も出てきています。
ただ、ここで気を付けないといけないのが、色の付き具合。。。
実は樽貯蔵の泡盛は、一定の色合いより濃くなると販売できなくなってしまうのです。酒税法の壁です。
それ故色の濃い泡盛は何らかの方法で薄めたり、リキュールとして泡盛と名乗らずに販売する方法をとることになります。
近年は敢えて糖分を加えたりしてリキュールとして販売するメーカーも増えてきました。
甕貯蔵

甕といえばThe 泡盛という感じもしますが、まさにその通り。
甕に含まれる土由来のミネラルや空気が溶け出し、液体と混ざり合うことで独特の風味を生み出します。また、熟成が進みやすいという点も大きなメリットとしてあげられ、同じ年数を寝かせたモノでも甕とそれ以外では違いが出てきます。
熟成が進みやすいことでまろやかで飲みやすい泡盛になる一方、ミネラルが溶け込むことでより泡盛らしい濃厚な風味に育つのも甕熟成の特徴。だから飲みやすいのに味はしっかりしているお酒が多いのです。
しかし、管理が難しいのも甕熟成。定期的にふたを開けて撹拌したり、場合によっては仕次ぎを行うことで一定のアルコール度数を保つ必要があります。その為、大量生産も難しく手間がかかるために販売価格が上がってしまうのも難点。
ご家庭で甕を使って熟成させる場合も同様に、定期的な管理を心がけてください。
タンク貯蔵

今最も一般的な方法がステンレスタンクを用いた貯蔵。
一番のメリットが他の方法に比べて管理がしやすいこと。そして外部の環境の影響を比較的受けにくいので、風味に影響を与えることも少なくすっきりした味わいに育ちやすい特徴があります。
管理の手間が少ない分価格を抑えることが出来るのもタンク貯蔵のメリットですね。
デメリットというと大げさですが、他の貯蔵方法に比べ熟成には時間がかかることが多いです。どうしても外部との接触を遮断しているのでしかたのないことではありますが、これが管理を楽にしている要因でもあると考えると、一長一短、トレードオフの関係といった感じですね。
泡盛選びの基準に
古酒や銘柄を基準に泡盛選びをする方は多いと思いますが、実際には味のわからない銘柄も多くありますよね?
そんなときは貯蔵方法・熟成方法を見てみてください。もちろん酒造所によって原材料・製法も様々ですので全てに当てはまるわけではありませんが、貯蔵方法を知るだけで大まかなテイストを想像することが出来ます。
最近では複数の熟成方法の泡盛をブレンドして双方の良いところを取り入れた泡盛も発表されています。
実際にはボトルにそういった情報が記載されていないことも多いのですが、当サイトの商品紹介の際は極力その情報も掲載するよう心がけております。
皆様の泡盛ライフに少しばかりの豊かさをお伝えできれば幸いです。